こんにちは、松戸整体院院長の清水です。
最近、スマートフォンの画面やパソコン作業が増えて、ふと遠くを見たときに「あれ?なんかボヤけて見えるな…」と感じたことはありませんか?
この違和感、年齢のせいだとか、単なる疲れ目だと思って放置している人も多いかもしれません。
でも、もしかしたらそれ、「仮性近視」のサインかもしれません。
仮性近視は、一時的にピント調節機能がうまくいかなくなって、近視のような症状が出る状態のこと。
多くの方が「もう近視が始まったかも…」とあきらめてしまいがちですが、実は生活習慣や身体の使い方を見直すことで、元に戻せる可能性がある状態です。
この記事では、仮性近視の正体や原因、一般的なケアの限界、そして整体や視覚調整による新しいアプローチについて詳しく解説していきます。
「最近、視力が落ちた気がする…」「遠くがぼんやりしてきた…」そんなあなたにこそ、読んでいただきたい内容です。
目次
「仮性近視」とは何か?本物の近視との違い

仮性近視とは、正式には「調節緊張」とも呼ばれる状態で、目のピントを調節する筋肉(毛様体筋)が過度に緊張していることによって、遠くが見えづらくなる症状です。
本当の近視と違うのは、眼球そのものが変形しているわけではなく、機能的な問題だという点です。
私たちの目は、近くを見るときに毛様体筋が収縮してレンズ(水晶体)を厚くし、ピントを合わせます。
仮性近視は、その毛様体筋が長時間緊張状態のままになり、遠くを見ようとしても筋肉がうまく緩まず、ピントが合わなくなってしまうのです。
子どもから大人まで幅広い世代に見られる仮性近視ですが、特にスマートフォンやタブレットを長時間使う現代では、誰にでも起こりうる問題です。
この段階で対処すれば、進行を止めたり改善することも可能ですが、放っておくと“本物の近視(軸性近視)”へと進んでしまうこともあります。
だからこそ早めの対応が重要なのです。
なぜ起こる?仮性近視の本質的メカニズム

多くの人は、仮性近視の原因を「画面の見すぎ」「暗い場所での読書」など、目そのものの使い方だけにあると考えがちです。
確かに、それらも一因ではありますが、実はもっと深いところに本質的な原因が潜んでいます。
仮性近視の根本には、「自律神経の緊張」と「姿勢の崩れ」が密接に関係しています。
毛様体筋の緊張は、副交感神経の過活動や交感神経とのバランスの乱れによって起こります。
長時間同じ姿勢で作業し、呼吸が浅くなり、首肩がこり、全身の循環が悪くなった結果として、目の筋肉にも過剰な緊張が伝わってしまうのです。
また、猫背や前かがみの姿勢では、首や眼球の位置もズレ、視覚情報の処理がうまくいかなくなります。
身体の歪みが目の働きにまで影響しているというのは、意外に思われるかもしれませんが、整体的な視点ではごく自然な理解です。
つまり仮性近視は、目の使いすぎだけではなく、「身体全体の使い方」や「ストレスの蓄積」「自律神経の状態」といった複合的な要因によって引き起こされるのです。
目薬や遠くを見るだけでは改善しない理由

「目が疲れたら目薬をさせばいい」
「遠くを1分間見るようにすれば大丈夫」
こうしたケアは仮性近視に対してよく言われる対処法ですし、実際にやっている方も多いと思います。
しかし、これらはあくまで一時的な緩和策に過ぎません。
なぜなら、仮性近視は“目だけの問題”ではないからです。
いくら目薬をさしても、毛様体筋の緊張を根本的にとることはできませんし、遠くを見ても筋肉が固まりきっていたら、切り替えがうまくいかないのです。
しかも、多くの人は日常生活の中で、再びすぐにスマホやパソコンに戻ってしまいます。
また、アイマッサージやホットタオルなども目の血流を一時的に良くするには有効ですが、首や肩、呼吸、脳の使い方、姿勢などが改善されない限り、本当の意味で目の筋肉はリセットされません。
つまり、「目だけをケアする」という考え方では、仮性近視の根本的な改善にはつながりにくいのです。
全体性を見て、目の緊張を作り出している背景から整えていくことが、根本改善への道筋となります。
目だけではない、全身のバランスが影響している

仮性近視の改善を目指すなら、身体全体のバランスに注目することが不可欠です。
実際、当院に来られる方の多くは、目だけでなく、首・肩・背中の緊張が非常に強く、さらに呼吸が浅くなっている傾向があります。
人間の視覚は、「目」だけで完結しているわけではありません。
目の奥には視神経があり、そこから情報が脳に送られ、脳で「見る」という処理を行います。
さらに、姿勢や平衡感覚、頭の位置などの情報も連動して、「どのように世界を見るか」が決まるのです。
例えば、首が前に出た姿勢が続くと、眼球の位置も前方へ引っ張られ、ピントの調整が難しくなります。
呼吸が浅くなると、自律神経のバランスも乱れ、毛様体筋の緊張も取れにくくなります。
つまり、目の働きは、身体の構造と神経系の影響を強く受けているのです。
整体や視覚調整では、こうした全体のつながりを見ながら施術を行います。
目そのものに触れるだけでなく、首の位置、呼吸の深さ、骨盤の安定性など、あらゆる角度から“見る力”を支える土台を整えていくのです。
なぜ、病院では「異常なし」と言われるのか?

松戸整体院には、眼科で「異常なし」と診断されたものの、「でもなんとなく見えにくい」「視力が落ちた気がする」という不安を抱えて来られる方がたくさんいます。
共通しているのは、「機能的な問題」が起きているにも関わらず、それが検査には現れにくいという点です。
病院の検査では、器質的な異常(病変や損傷)があるかを確認するため、筋肉の緊張や神経のバランスまでは測定しません。
また、仮性近視の多くは“時間帯によって視力が変動する”“リラックス時は回復する”といった特徴があるため、検査時のコンディションによっては正常に見えてしまうこともあります。
だからこそ「何もないって言われたけど、でも不安」「このまま放っておいたらどうなるの?」という気持ちを抱える方が多いのです。
松戸整体院ではそうした“未病”や“機能的なアンバランス”を丁寧に評価し、身体全体からアプローチすることで、根本的な改善を目指しています。

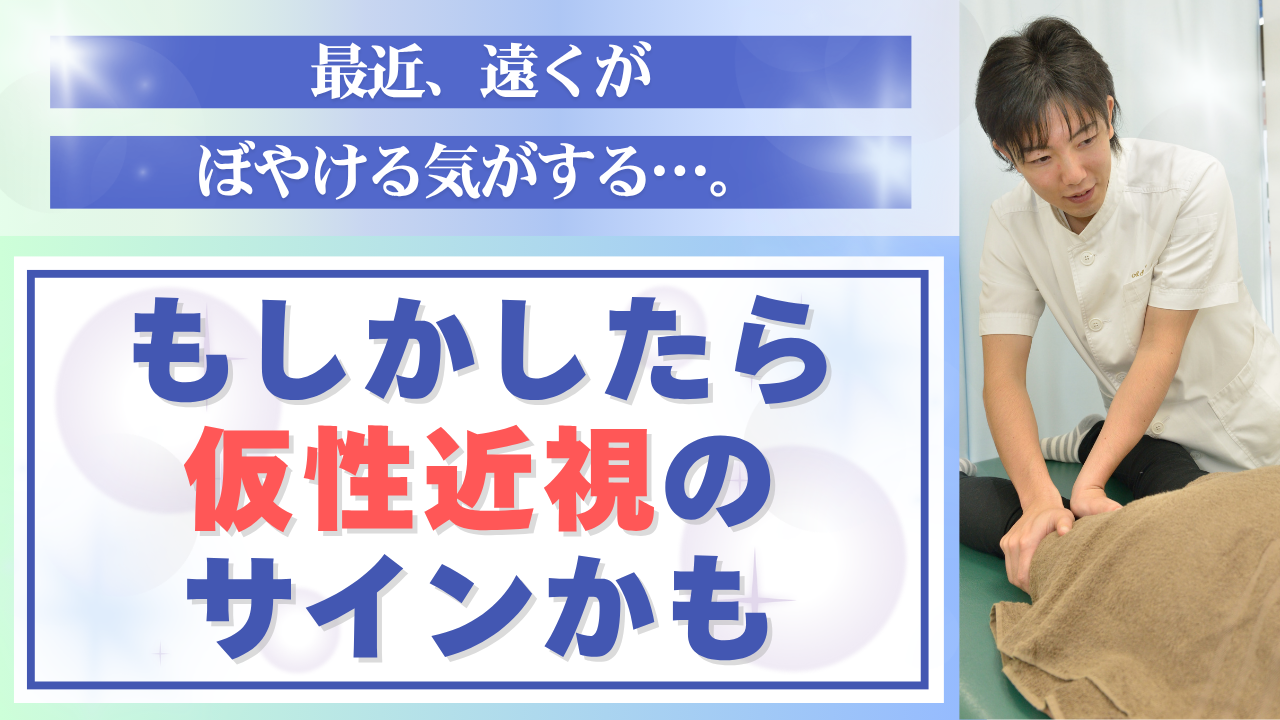
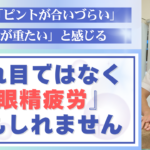
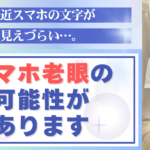
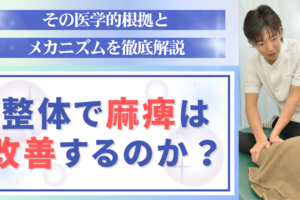

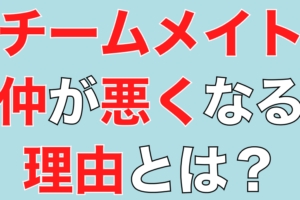
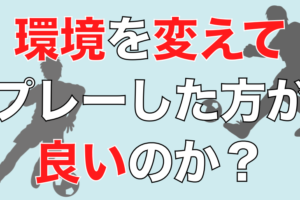
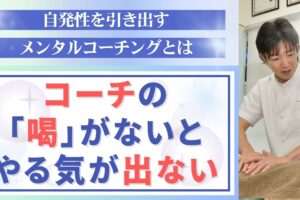
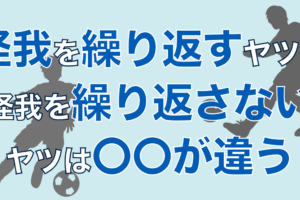
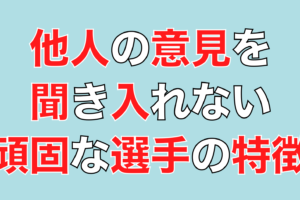

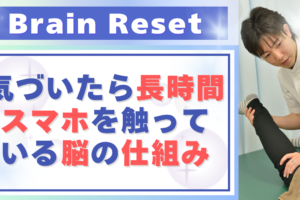




 松戸整体院院長 清水亮彦
松戸整体院院長 清水亮彦
コメントを残す